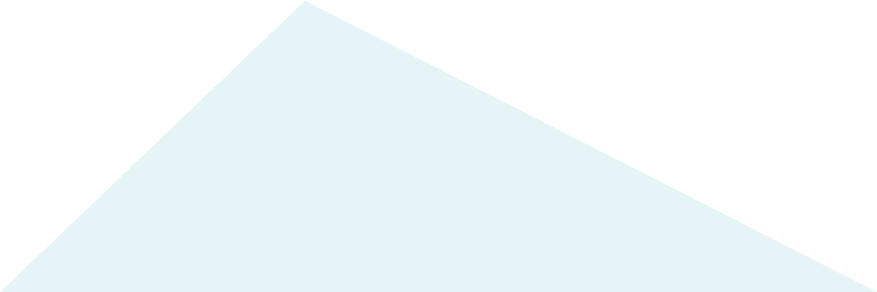
こういった場合、わたしたちはしばしば「デザイン」という語の和訳に試みることがある。かつて明治期の日本人が「Philosophy」を「哲学」と訳したり「Society」を「社会」とすることでそれを理解してきたように、「デザイン」という概念にもまたいくつかの和訳があるはずである。広辞苑によれば「デザイン」は、
(1)下絵。素描。図案。
または、
(2)意匠計画。生活に必要な製品を製作するにあたり,その材質・機能および美的造形性などの諸要素と,技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画。
とある。「図案」や「意匠」という言葉は聞き覚えがあるだろうから(1)は比較的わかりやすいだろうがどうも狭義的にすぎるし、(2)では正反対に「総合的造形計画」というなんとも漠然とした言葉に置き換えられている。
ところで、ドイツ語で思想した哲学者ヴィレム・フルッサーは「デザイン」という語について、次のように説明している。
名詞としてそれは、とりわけ「計画」「プラン」「意図」「狙い」「悪だくみ」「陰謀」「形」「基本構造」を意味するが、これらすべてやその他の意味はどれも「策略」や「詐術」に関係している。動詞としての意味には、とりわけ「何かを考え出す」「装う」「下絵を描く」「スケッチする」「形づくる」「戦略的に処置する」がある。
(ヴィレム・フルッサー『デザインの小さな哲学』鹿島出版会・二〇〇九年)
フルッサーのこの指摘は「デザイン(Design)」の語源をラテン語の「designare」に求めて言ったものだが、これは実に示唆に富んでいる。「designare」は「計画を記号に表す」という意味を持った単語だが、ここで「計画」とみなされているもののなかには「意図」「狙い」「構成」そして「詐術」や「陰謀」が含まれているということだ。このように「デザイン」を「詐術」として捉えてみることは、わたしたちにとって「デザイン」を理解することの一助になりはしないだろうか。
フルッサーが「詐術」の対象としたものには例えば「自然」がある。
技術によって自然を策略にはめ、人工的なものを通して自然的なものを上回り、われわれ自身にほかならない神がそこから降臨してくるような機械を組立てること。要するに、デザインはすべての文化の背後にあるものだ。それは、狡猾なやり方で自然に制約された哺乳動物であるわれわれを、自由な芸術家に変えるのである。(同前)
いま一度、この視点に立ってデザイン史を読み直してみよう。
例えば縄文の火焔土器、未開部族の入墨、密教の曼荼羅、民族衣装に用いられるテキスタイル――。こうした前近代のデザインにはかならずや何かしらの自然的なコードが隠されていて、それは時に噴出する溶岩であったり、波の描く模様であったり、また巻貝のらせん状のフォルムであったりする。ジョージ・ドーチは『デザインの自然学』(青土社・一九九四年)において、こういった自然界のフォルムと芸術や建築におけるプロポーションとの相補的な関係性を明らかにしているが、つまるところ、これらはすべて自然の脅威に対峙するために人類が生み出したある種の呪術だったのではないかなどと考えてしまう。“狡猾な”自然をあざむきながら自然界における自身の居場所を確かなものとするために、人類は時に動植物を模したり火焔や稲妻を描いたりしてきたのではないだろうか。さらにいえば、自然に対してあまりにひ弱な自分自身をもあざむくためにである。
おそらく、「デザイン」の原点とも呼ぶべき風景がここにある。私たちの文化には決まってポイエーシス(自然を対象とした「制作」)が根底にあるはずである。でなければ近代以前のどんな文様も土器も、衣服や建築のモードも何ひとつとして説明できない。「デザイン」とはつまり、そうしたポイエーシスの試みに他ならないのではないだろうか。
残念なことに、私たちが「デザイン」を理解するための根拠としてきた近代以降のデザイン教育はこのことをあまりに軽視しつづけてきた節がある。確かに、急速に変化しつづける生活環境を背景として誕生したモダン・デザインのデザイナーに求められたことは、建築にしろ工業製品にしろ宣伝広告にしろ、それらの「作品」によって私たちの生活世界を「啓蒙」する指導者としての役割であったかもしれないが、そのことばかりを追いかけていては到底「デザイン」という行為にも、また「デザイン」されたモノの本質にも迫ることはできないはずだ。このことが、あるいは「デザイン」という語を曖昧にしている一因なのではないか。
近代のデザインは、永らくポイエーシスな試みであった「デザイン」に時間とコストと市場の計画概念を持ち込んだ。途端「デザイン」からはかつてのような呪術的なコードはすっかり影をひそめてしまい、代わりにポイエーシスとは対照的な「プラクシス」(人間を対象とした「実践・行動」)的なものが立ちあらわれてくる。
しかし、だからといって「デザイン」が詐術でなくなったわけではない。先述したような作家・作品論的なデザイン史の論者であるニコラス・ぺヴスナーに対して一貫して批判的な立場をとったアドリアン・フォーティは、デザイン史に社会文化論的な視点を持ち込むことで近代デザインの「詐術」をことごとく看破した。例えばこうだ。産業の機械化により高度に分業化された産業は「職場」や「工場」を生み出す。家内制手工業の終わりである。すると「家庭」はこうした「労働をする場所」と対照的に、人間に癒しを提供する場へと変わっていく。そこで家具や調度品は自分自身を安らげるため、自身の尊厳を回復するためのデザインが求められるようになり、それはやがて現代に通じる家庭像をともないながら「家政」という領域をも生み出すのである。
このように近代の「デザイン」は近代社会が抱える様々な観念、イデオロギーやテクノロジー、あるいは市場の論理に絶えず影響を受けながら決定されていったというのがフォーティの見方だ。やはりそこでも「デザイン」は近代社会のシステム、資本主義や進歩主義的なモードのなかでわたしたちの生活文化を形成するために機能している。異なっているのは、相手とするのが自然ではなく、社会システムであったり、またそれを作り出した人間自身であるという点だけだ。
勘違いしてはいけないのは、縄文土器も近代のオフィス家具も、例えばいまわたしたちが手にしているスマートフォンも、そのあいだには何ひとつとして断絶はないということだ。確かに近代以降の「デザイン」は絶えず時間とコストと市場の計画概念のなかで問われ、私たちの生活環境を向上させ続ける宿命を背負ってきたが、そういえどやはり「デザイン」は常に自然や、システムや、異なった文化文明とのコミュニケーションを成立させるために使われてきた詐術であることに変わりはない。そこではデザイナーは指導者ではなく、様々な「運動(体)」のなかで世界と対話をする「調停者」であるといえる。いま改めて「デザイン」を問おうとしている私たちはこのことを決して忘れてはならないだろう。そうした視野を持って「デザイン」を眺めれば、少なくともいまほど「デザイン」という言葉の前に戸惑うことはなくなるはずなのだが。
写真をはじめとしたメディアを中心に思想を展開。
主な著作に『写真の哲学のために:テクノロジーとヴィジュアルカルチャー』『サブジェクトからプロジェクトへ』など。
ハンガリー、スウェーデン、イラン、アメリカなどで長年にわたって建築に携わる。北西岸ユング心理学友の会創設者。
ロンドン大学、ケンブリッジ大学の教授職を歴任。
代表的な著作に『モダン・デザインの展開 モリスからグロピウスまで』他、イギリスの建築に関する著作多数。
現在、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンにて建築史教授。
建築・デザインに関する論文を多数執筆。主な著作に『欲望のオブジェーデザインと社会1750以後』『言葉と建築』など。